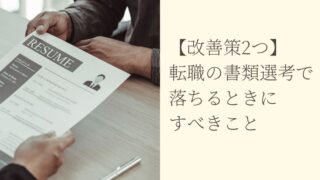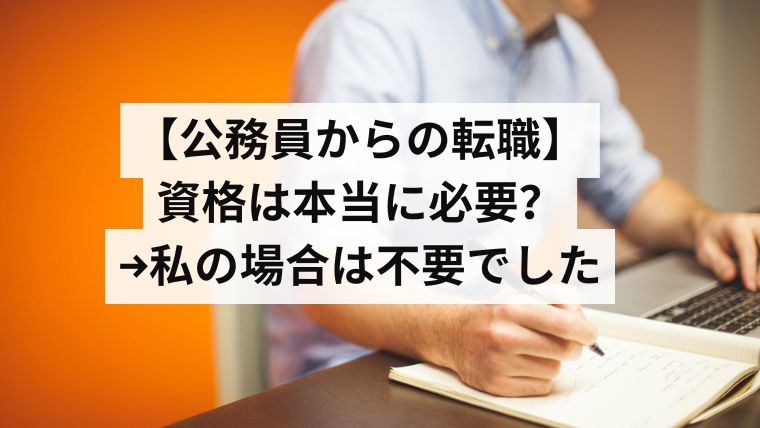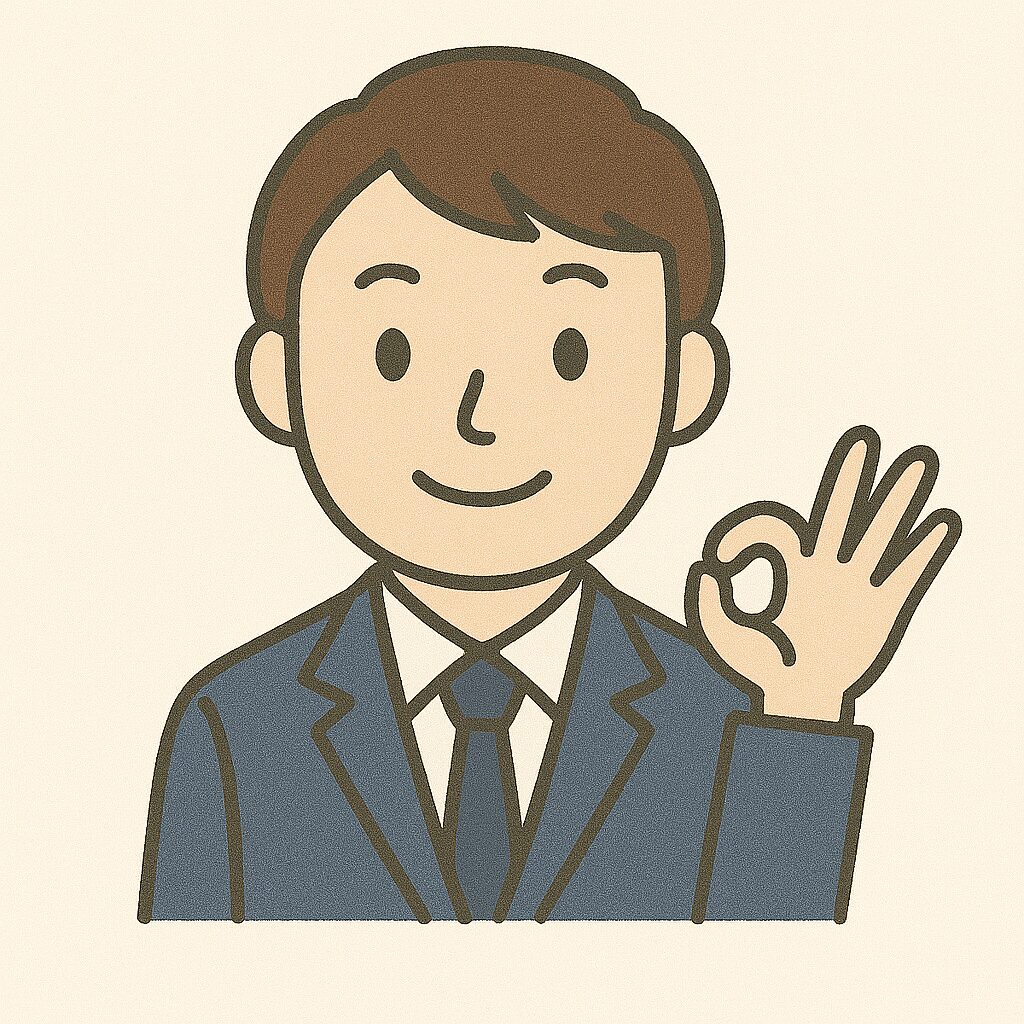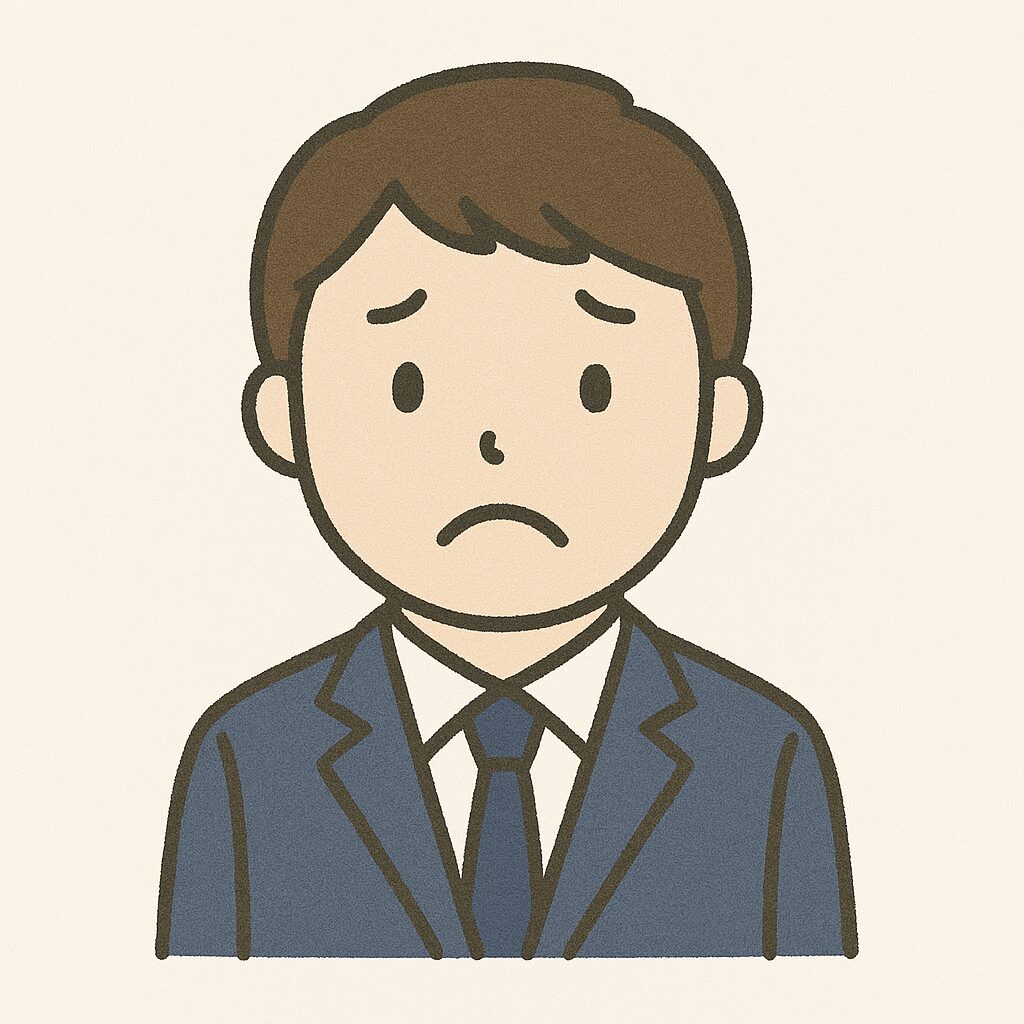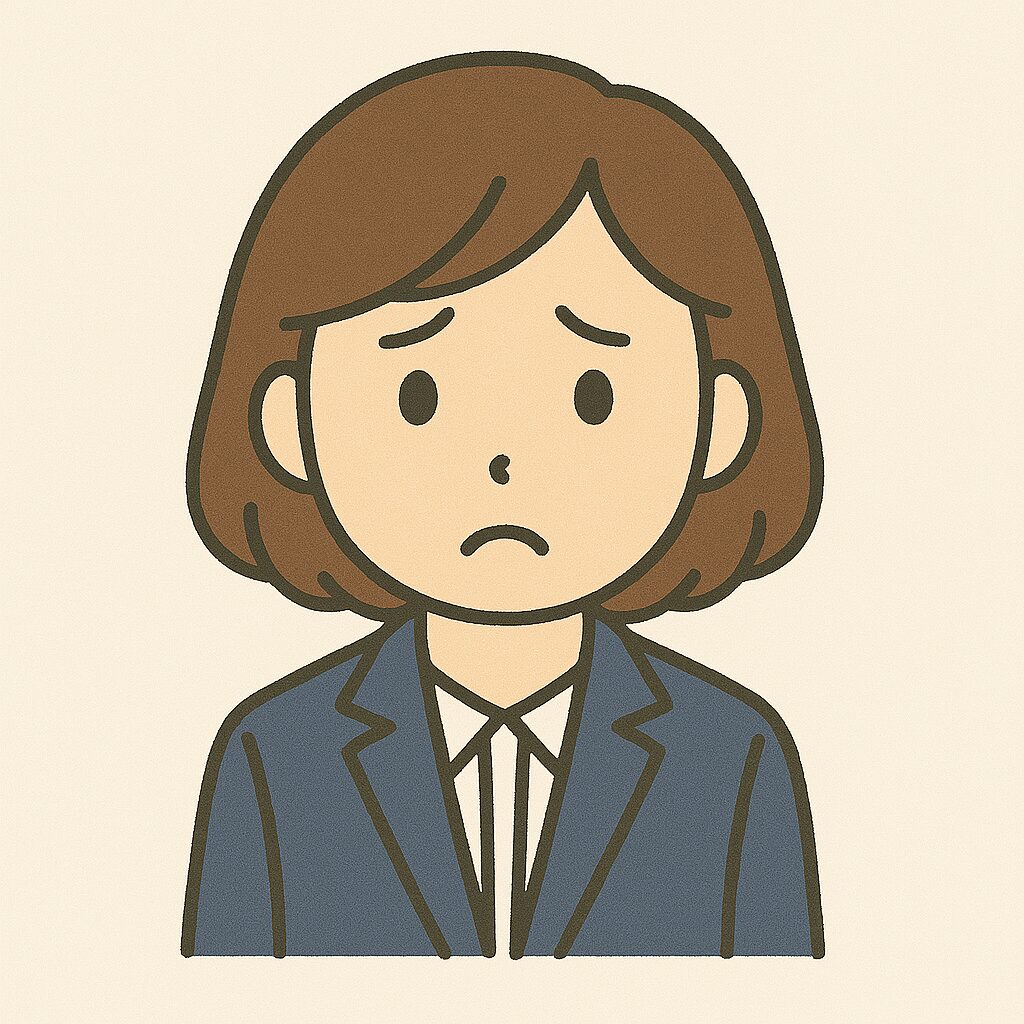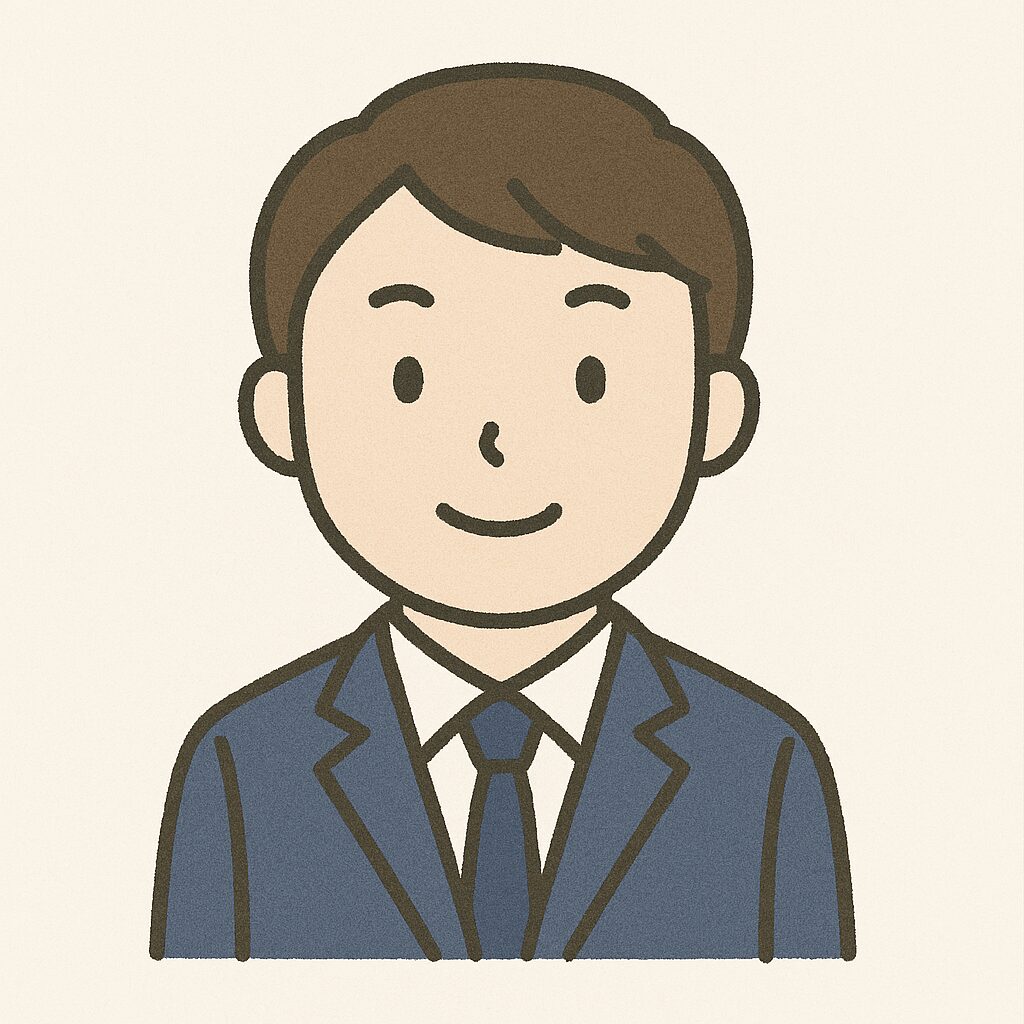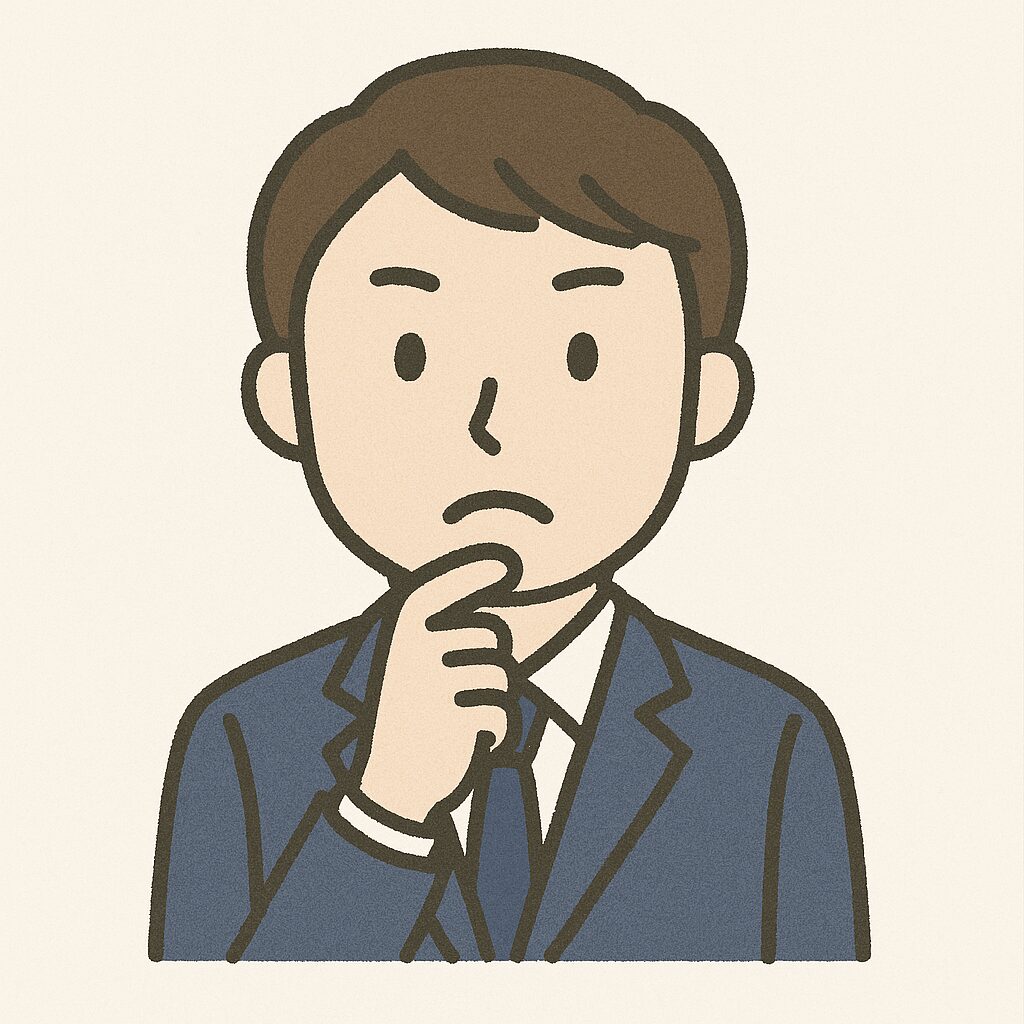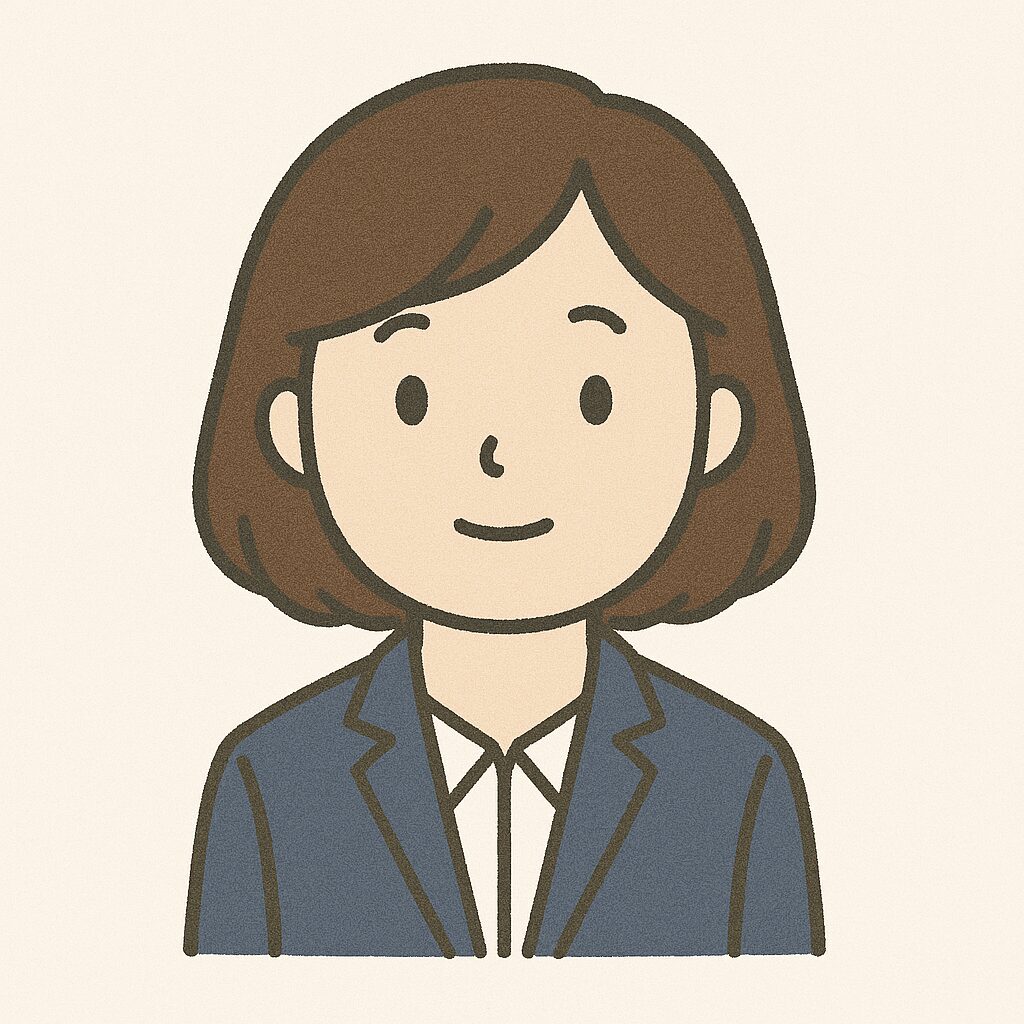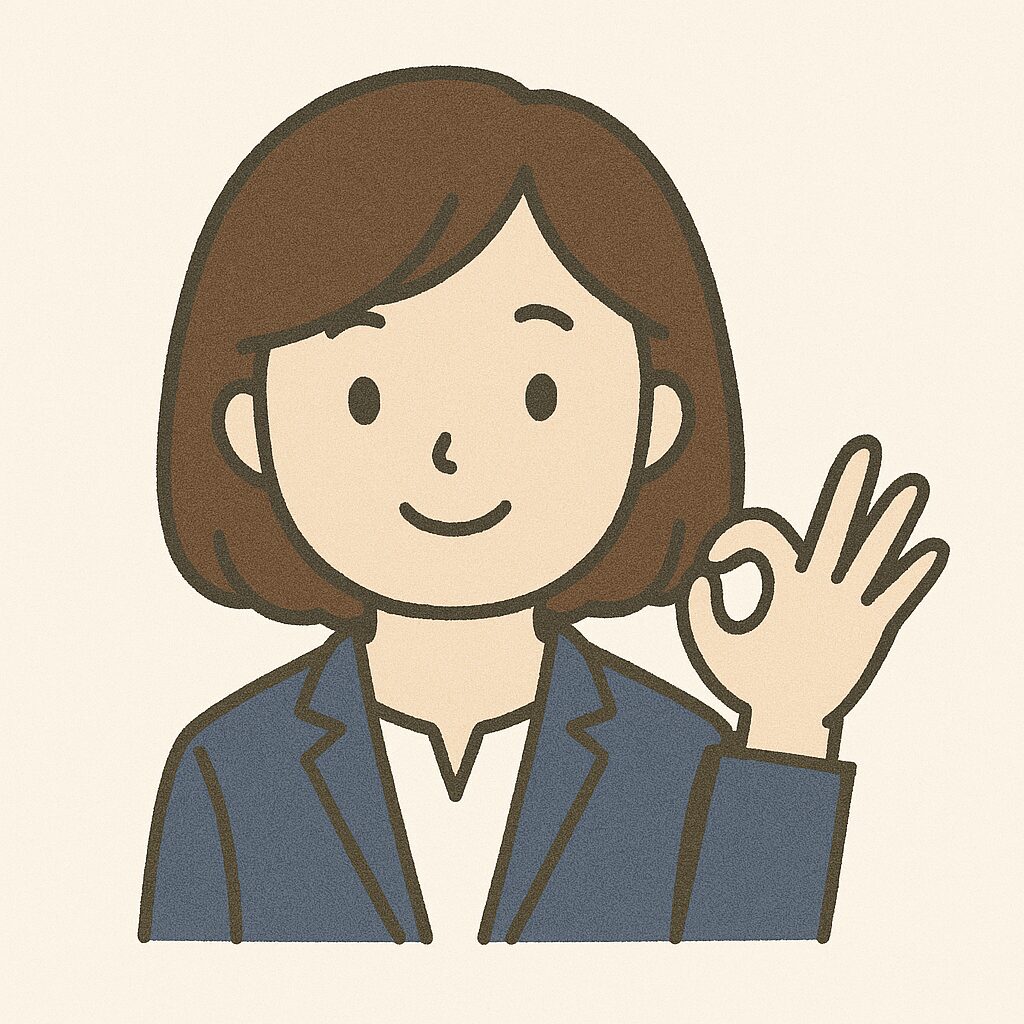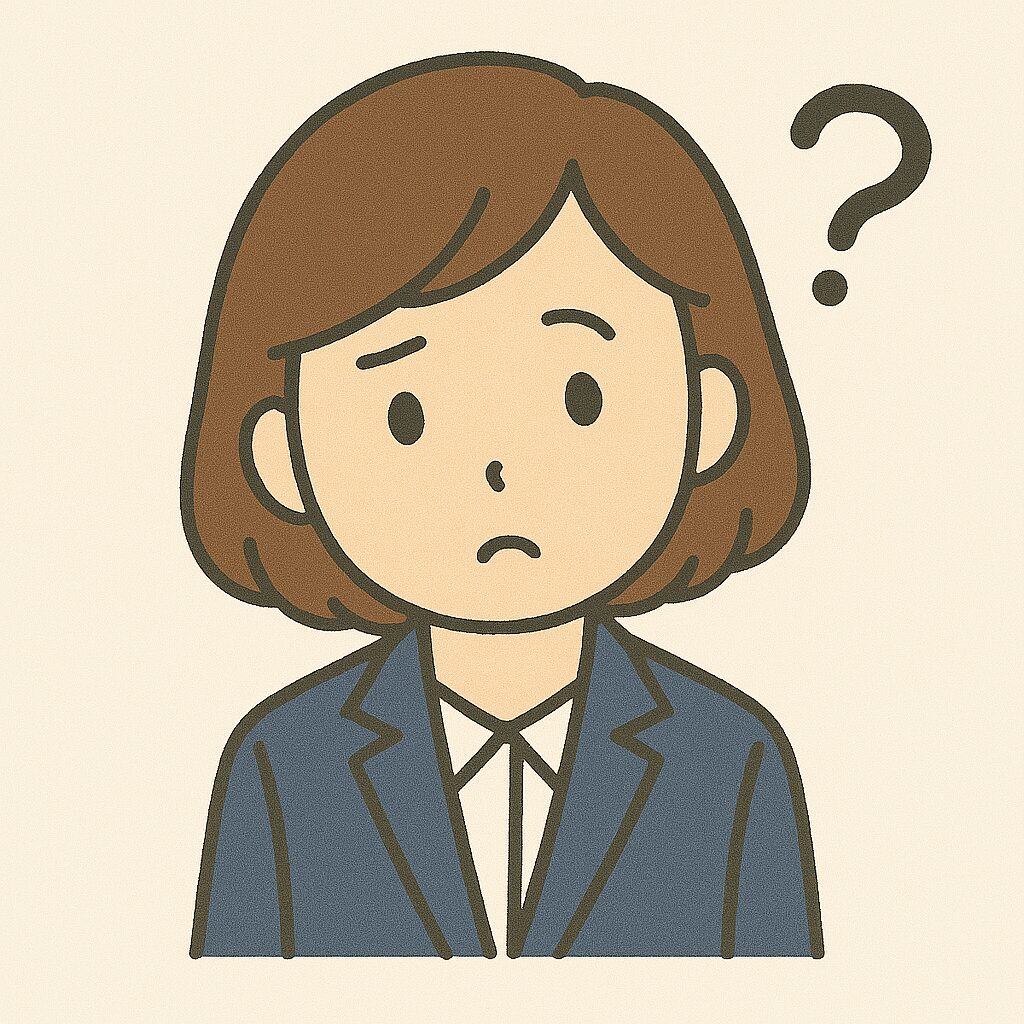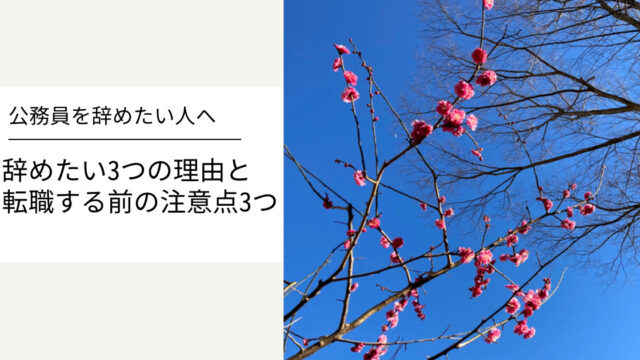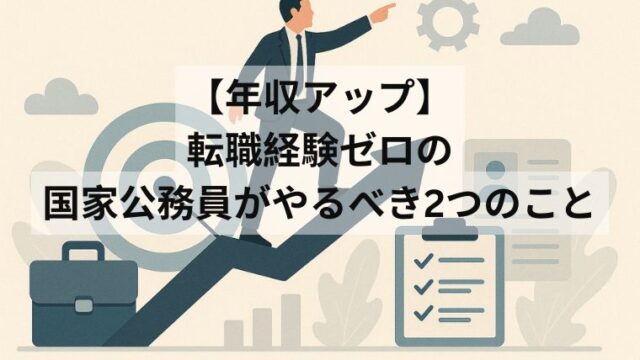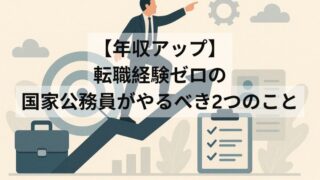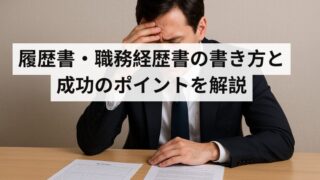「公務員から転職したいけど、自分にはアピールできるスキルがない…」
「資格でも取っておかないと、民間企業では相手にされないかも…」
そんな不安を抱えて、「公務員から転職 資格」と検索してこの記事にたどり着いたあなたへ。
結論からお伝えします。資格がなくても転職はできます。
2回転職しましたが、どちらも資格と関係のない会社です
資格よりも圧倒的に大切なのは「これまでの仕事で、どんな工夫をして仕事をしてきたか」なんです。
この記事では、私自身の転職経験をもとに、
- ・なぜ資格に頼らなくてもよかったのか
- ・企業が見ているポイントはどこか
- ・あなたの「強み」の伝え方
をお伝えしていきます。
転職に向けて、最初の一歩を踏み出すためのヒントが詰まっていますので、お役に立てれば幸いです。
はじめに:「資格を取れば転職できる」という幻想
「今の仕事が楽しくない。公務員を辞めたい」
「でも、どうすればいいんだろう……」
そんな思いを抱えてネットを検索しているうちに、あなたはこう思い始めたのではないでしょうか?
やっぱり転職するには、資格が必要だよな…
履歴書に書けるものが何もないから、まずは資格を取ろうかな…
この考え方、実は多くの公務員がハマってしまう「転職準備あるある」です。
かく言う私も、同じように「転職するためにはまず資格を」と思っていた一人でした。
公務員からの転職で多くの人が「資格」にすがる理由
公務員として働いていると、民間企業という未知の世界に足を踏み入れるのは不安だらけですよね。
私自身が持っていた不安は、つぎのとおりです。
- ・売上やコストカットなど、数字で説明できる実績がない
- ・ずっと公務員だったから、特別なスキルはない
- ・民間企業で通用する自信がない
- ・何か“肩書き”があった方が評価されそう
その不安を埋めるために、多くの人が「まず資格を取ろう」と考えます。
資格の勉強は「自分を高めている気になれる」し、「行動してる実感」も得られます。
公務員試験を突破した人は基本的に学ぶ力が高いので、努力すれば大抵の資格は取れてしまいます。
だからこそ、多くの人が資格取得に走ってしまうんだね
実体験からわかった「資格がなくても大丈夫だった」という事実
「資格を取れば、書類選考で有利になるだろう」
「TOEICの点数が高ければ、企業から評価されるはずだ」
そんな期待を抱きながら、私はTOEICの受験と簿記の資格を取りました。
履歴書に書ける資格がなかったから、増やしたかったんだよね…
でも、結論から言えば、それらの資格が私の転職活動で評価されたことは一度もありませんでした。
むしろ、「こんなに頑張って資格を取ったのに、まったく見られないんだ…」という現実に、少しショックすら覚えました。
私が転職で痛感した「資格」と「実務経験」に関するギャップは、次のとおりです。
それぞれ詳しく、私自身の転職経験を踏まえた実感をお伝えします。
応募したい求人で求められる資格がない
興味のある求人を見ていると、求められる資格がないことに転職活動を始めてから気づきました。資格だけじゃなく、大卒じゃなくても高卒なら応募できる求人も全体の70%以上だったんです。
私の場合、資格の有無で求人に応募できないことはありませんでした
TOEICや簿記のことは、面接でも一切聞かれない
私が転職活動を始めたとき、TOEICは840点、簿記は3級を持っていました。履歴書の資格欄には、しっかりとそれらを書き込みました。
せっかく時間をかけて取得した資格をアピールしたかったんです
でも、返ってくる反応はゼロ。
書類選考に通ったときも、落ちたときも、資格がどう影響したのかは一切わからないまま。
面接の場でも、TOEICや簿記に触れられることは一度もありませんでした。
どの企業でも、面接で聞かれたのは以下のようなことばかりでした。
- 「今までどんな業務に関わっていましたか?」
- 「その業務の中で工夫したことはありますか?」
- 「チームでどういう役割を担っていましたか?」
- 「あなたの強みは何ですか?」
資格だけじゃ企業は評価してくれないってことだね
逆に言えば、「資格」だけでは企業に自分を売り込めない、ということです。
資格そのものより、「仕事でどう動いてきたか」が見られている印象でした。
転職後に採用してくれた人に「なぜ自分を採用してくれたのか」を聞いてみたのですが、一番のポイントは「チームの中でうまく人間関係を作って、お客様への対応も問題なくやってくれそうか」という点でした。
面接の担当者も資格については注目してなかったみたいです
転職後も資格が役立った場面はなかった
転職してから資格が役に立つ場面もあるかなと思ったのですが、英語や簿記の資格が活きる場面はゼロ。
配属されたのが海外担当部門でも、会計担当部門でもないから、英語や簿記の資格を使うことがないのも当たり前だね…
役立ったのはむしろ、
- ・タスクを抜け漏れなく整理して、期限までにやり切る力
- ・調整役として、周囲とコミュニケーションをとる力
- ・わからないことを積極的に学びにいく姿勢
といった、公務員の実務の中で鍛えられていたスキルでした。
資格よりも、日々の仕事の中で「当たり前にやっていたこと」の方が武器になったね
あなたの「価値」を最大化する!経験・実績の効果的なアピール術
「資格がなくても転職はできる」
そうは言っても、「じゃあ、自分は何を武器にすればいいの?」と不安に感じますよね。
企業が本当に見ているのは、これまでの業務経験や、そこでどんな成果を出してきたかです。
私が実際に転職活動の中で工夫した、「経験や実績の伝え方」をまとめると、以下の3つです。
- 自分の強みを見つけて整理する
- 書類で“活躍するイメージ”を伝える
- 面接で「あなた自身の言葉」で語り切る
そして重要なのが、その経験を「民間企業の言葉」に翻訳することです。
たとえば、公務員で「地域住民との協議を行った」という業務。
これは民間で言えば「協業している企業との利害調整」や「対人交渉スキル」につながります。
単にやっていた業務の説明だけだと、不十分ってことだね
それが「どういう価値を生んだか」「どんなスキルの証明になるか」まで落とし込むことがカギになります。
公務員なのでお金に換算することはできませんが、地域住民との協議なら、次の項目を「具体的に」、「できれば数字で」説明できるとアピールが上手にできます。
- ・何回協議を行ったか
- ・延べ何人に対して協議を行ったか
- ・どんな要望が来て、どのように対応したか
これらを説明すると、面接担当者に「この人ならうちの会社に来ても活躍してもらえそう」と思ってもらえますよ。
応募書類、特に職務経歴書を書く段階でのポイントは、以下の2つです。
詳しい書き方は次の記事で説明しています。
「職務経歴書の書き方が分からない」
「何社も応募しているけど、書類選考で落ちてしまう」
という方は以下の記事を見ていただければと思います。
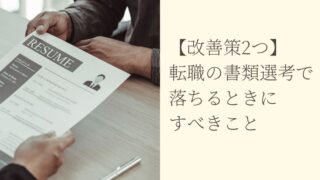
それでも気になる「資格」… どう向き合うべきか?
ここまで読んでも、やっぱり資格がないと不安な人もいますよね。
やっぱり資格ってあった方が安心じゃない?
資格があれば、選考で有利になることもあるんじゃ…?
と思った方もいるかもしれません。
その気持ち、よくわかります。私も「転職したい」と思った時、真っ先に取り組んだのがTOEICの勉強でしたから。
資格は目に見える実績であり、勉強している自分に安心感も与えてくれますからね。
ここでは、そんな「資格とどう付き合うべきか?」について、私の考えを整理してお伝えします。
資格は「自信」や「知識整理」のためのお守り程度と心得る
資格を取ること自体が悪いわけではありません。
実際、私も資格の勉強を通じて「知らなかったことを学べた」と感じることもありました。
ただ、重要なのは「それをどう使うか」です。
- ・資格を取得した後、仕事にどう役立つのか?
- ・その資格が、自分の進みたい道や働きたい企業に必要なものか?
資格取得に向けて努力する前に、上記2点を考えることが時間と労力の節約になります。
資格は“転職成功の切り札”ではありません。資格を持っていれば自動的に転職できるわけではありません。
あくまでも、「自分の理解を深めるため」「自信をつけるため」の補助ツールくらいに捉えるのがちょうどいいです
取得するなら目的を明確に
資格を取るなら、「なぜその資格を取るのか?」をはっきりさせることが超重要です。
たとえば、
- 宅地建物取引士 → 不動産業界に転職したい場合は有利
- 中小企業診断士 → コンサル・経営企画を志望している場合に有効
- 社会保険労務士・行政書士 → 専門職や士業としてのキャリアを目指すならオススメ
つまり、「行きたい業界・職種があって、そのために必要だから取る」という順番が正解です。
逆に、「とりあえず資格を取ってから考える」は、時間もお金も失い、転職も遠回りになるリスクがあります。
正直、ほとんどの転職に資格は不要だと思います
資格の勉強をするより、履歴書や職務経歴書の改善をしたり、実際に求人に応募したりした方が早く転職できる気がするね
✅ 結論:資格に頼らず、経験を活かす転職をしよう
この記事のまとめは、以下のとおりです。
- ・民間企業が見ているのは、「資格」ではなく「現場でどう動けるか」
- ・資格はあくまでお守り程度。主役はあなたの“行動”と“成果”
- ・自分の強みと経験を活かすための準備に、力を注いでほしい
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
この記事が、あなたの転職活動の不安を少しでも軽くし、
「資格がないから…」ではなく、「今の自分でも価値がある」と思えるきっかけになれば幸いです。
それでは、また。